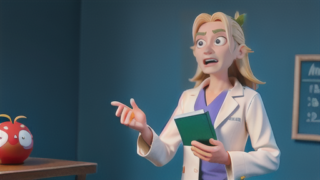看護技術
看護技術 褥瘡:予防と対策について
- 褥瘡とは褥瘡は、一般的に「床ずれ」として知られる症状です。これは、長時間同じ姿勢を続けることで、特定の部位、特に骨が出っ張っている部分に体重がかかり続け、その部分の血流が悪くなることで発生します。皮膚やその下の組織が、まるで押しつぶされたように傷ついてしまうのです。褥瘡は、寝たきりの方や車椅子を利用している方など、長時間体を動かすことが難しい方に多く見られます。このような状態では、体重がかかりやすいお尻や背中、かかとなどに褥瘡ができやすくなります。また、栄養状態の悪化や、糖尿病などの病気によって、皮膚の抵抗力が弱まっている場合も、褥瘡ができやすくなるため注意が必要です。褥瘡は、初期段階では皮膚が赤くなる、または紫色に変色するなどの症状が現れます。さらに悪化すると、水ぶくれや皮膚のびらん、潰瘍などが生じ、場合によっては、そこから細菌が侵入し、感染症を引き起こすこともあります。感染症を合併すると、発熱や悪寒、患部の痛みや腫れなどの症状が現れ、重症化すると命に関わることもあります。褥瘡を予防するためには、体位変換をこまめに行い、圧迫されている部分を解放することが重要です。また、栄養バランスの取れた食事を心がけ、皮膚を清潔に保つことも大切です。褥瘡が疑われる症状が見られた場合は、自己判断せずに、速やかに医師に相談しましょう。