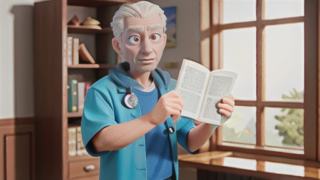その他
その他 内臓痛:体の奥からのサイン
- 内臓痛とは
内臓痛とは、胃や腸、肝臓といったお腹の中の臓器に異常が起きた時に感じる痛みのことです。私たちの体は、大きく分けて体の表面を覆う組織と、体の中に収められた臓器によって構成されています。体の表面を覆う組織には、皮膚や筋肉などが含まれます。一方、体の中に収められた臓器は、食べ物を消化吸収する消化器や、呼吸をするための呼吸器、血液を循環させる循環器など、生命維持に欠かせない重要な役割を担っています。
内臓痛は、このような体の中の臓器で発生する痛みのことを指し、体の表面に近い場所で感じる皮膚の痛みや筋肉の痛みとは異なる特徴を持っています。例えば、皮膚や筋肉の痛みは、針で刺されたような鋭い痛みや、重いもので押さえつけられるような鈍い痛みなど、比較的痛みの場所を特定しやすいという特徴があります。一方、内臓痛は、痛みの場所が漠然としていて特定しにくく、「何となく重苦しい」「締め付けられるような感じがする」といった表現をされることが多いです。これは、内臓の痛みのセンサーが、皮膚や筋肉の痛みのセンサーに比べて数が少ない上に、体の広い範囲に分布していることが関係しています。そのため、内臓痛は、皮膚や筋肉の痛みと比べて、より鈍く、広がりのある痛みとして感じられるのです。