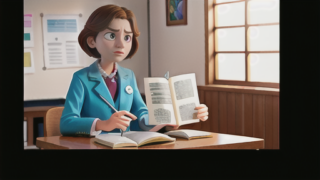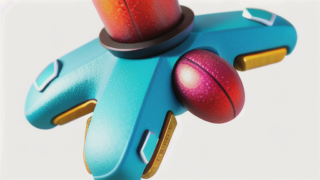資格・職種
資格・職種 医療現場の頼れるパートナー:医療クラーク
- 医療クラークとは医療クラークとは、病院やクリニックにおいて、医師や看護師が診療に専念できるよう、受付や事務業務全般をサポートする役割を担っています。患者さんにとっては、病院やクリニックに訪れた際の最初の窓口となり、スムーズな診療を支える、いわば病院やクリニックの「顔」とも言える存在です。具体的な業務内容としては、受付での患者さんの案内や電話対応、診療予約の管理、電子カルテへの情報入力、診療報酬請求業務などが挙げられます。医師の指示に基づいて、診断書や紹介状などの書類作成を行うこともあります。また、患者さんからの問い合わせや要望に対応するのも重要な業務です。医療クラークは、医療事務の専門知識に加え、患者さんとのコミュニケーション能力や、正確かつ迅速な事務処理能力が求められます。患者さんのプライバシーに関わる情報を取り扱うため、守秘義務を厳守することも重要です。近年では、医療機関におけるIT化の進展に伴い、電子カルテや医療事務システムを使いこなすためのスキルも必要とされています。医療クラークは、医療現場を支える重要な役割を担っており、患者さんが安心して診療を受けられる環境を作るために欠かせない存在です。