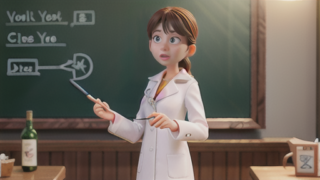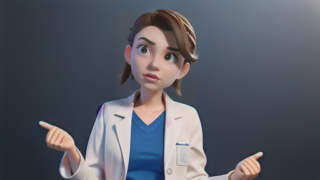産婦人科
産婦人科 男性らしさの源?男性ホルモンの役割とは
- 男性ホルモンとは男性ホルモンは、男性の身体に様々な変化をもたらし、生殖機能にも深く関わる重要な物質です。
思春期を迎えると、男性ホルモンの分泌量が急激に増加し始めます。 この変化は、男性の身体に目に見える形となって現れます。顔に髭が生え始め、声変わりが起こり、体毛が濃くなるなど、いわゆる「男性らしさ」が形成されるのは、この時期に分泌される男性ホルモンの影響によるものです。
男性ホルモンは、主に男性の体内で、精巣と呼ばれる器官で作られます。 また、少量ではありますが、副腎皮質と呼ばれる臓器や、意外にも女性の卵巣からも分泌されます。
男性ホルモンは、単に男性らしい身体を作るだけではありません。その役割は多岐に渡り、生命の根幹である生殖機能の維持にも大きく貢献しています。 精子を作る働きや性欲を維持する働きも、男性ホルモンの重要な役割の一つです。
さらに、男性ホルモンは、筋肉や骨の成長を促し、力強い身体を作る役割も担っています。 また、近年では、精神活動や感情の制御にも影響を与えている可能性が指摘されており、その働きは身体的な側面にとどまりません。
このように、男性ホルモンは男性にとって、心身両面に大きな影響を与える重要な物質と言えるでしょう。