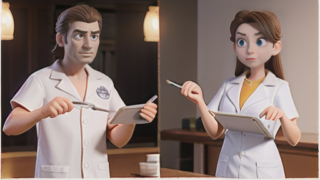消化器
消化器 腹膜炎:沈黙の脅威とその症状
- 腹膜炎とはお腹の内側を覆っている薄い膜、腹膜に炎症が起こる病気を腹膜炎と言います。この腹膜は、胃や腸などの臓器を外部の衝撃から守ったり、臓器同士が摩擦を起こさないように滑らかにする役割を担っています。健康な状態では、この腹膜は体内での役割をスムーズに果たしていますが、何らかの原因で細菌感染を起こしたり、刺激性の物質に触れたりすると、腹膜に炎症が起こってしまいます。これが腹膜炎です。腹膜炎の原因として最も多いのは、胃潰瘍や虫垂炎、大腸憩室炎といった消化器官に穴が開く病気です。これらの病気によって、消化器官の内容物が腹腔内に漏れ出すことで、腹膜に強い炎症を引き起こします。その他にも、 pancreatitisや外傷、手術後の合併症などが原因となることもあります。腹膜炎は、放っておくと命に関わる危険性も高い病気です。早期に発見し、適切な治療を行うことが非常に重要です。腹膜炎が疑われる症状としては、激しい腹痛、吐き気、嘔吐、発熱、腹部膨満感などがあります。これらの症状が見られる場合には、速やかに医療機関を受診するようにしてください。