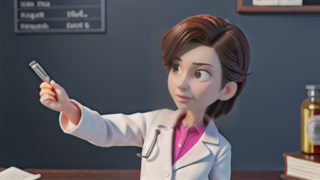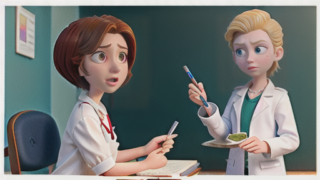健康寿命
健康寿命 日常生活の自立を支える:BADLとその評価
- 基本的生活動作能力(BADL)とはBADLとは、Basic Activity of Daily Livingの略称で、日本語では「基本的日常生活動作能力」と言います。人が健康的に、そして自立して日常生活を送る上で欠かせない、ごく基本的な動作を指します。具体的には、歩く、移動する、食事をとる、服を着替える、入浴する、トイレへ行くといった動作が挙げられます。これらの動作は、一見当たり前にできているように思えますが、加齢や病気、怪我などによって困難になる場合があります。 例えば、加齢に伴い筋力が低下すると、歩くことが困難になったり、立ち上がったり座ったりする動作がスムーズにできなくなったりすることがあります。また、脳卒中などの病気の後遺症によって、手足の麻痺が残ってしまうと、食事や着替え、トイレ動作が難しくなることもあります。 BADLは、これらの動作がどの程度できるかを評価することで、その人の自立した生活の度合いを測る指標となります。介護が必要な状態かどうかを判断したり、適切な介護サービスの利用を検討したりする際に、重要な要素となります。また、リハビリテーションの現場では、BADLの改善を目標に、様々な訓練が行われます。