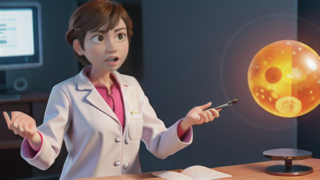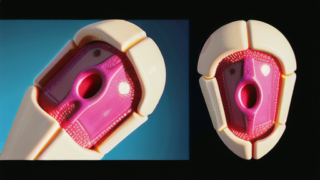脳・神経
脳・神経 記憶障害:脳の神秘に迫る
- 記憶障害とは何か記憶障害とは、脳の働きに何らかの問題が生じることで、記憶に関する能力に影響が出てしまう状態のことを指します。 私たちは普段の生活の中で、絶えず記憶の力を借りて生活しています。例えば、昨日食べた夕食を思い出す、新しい人の名前を覚える、朝起きたときに顔を洗う、といった行動も、すべて記憶が正常に機能しているからこそできることです。記憶障害が起こると、このような記憶に関連する行動に困難が生じ、日常生活に支障が出てしまうことがあります。 例えば、人の名前が出てこなかったり、約束を忘れてしまったり、時には自分が置かれている状況がわからなくなってしまうこともあります。 記憶障害には、様々な種類と程度があります。 ある特定の期間の記憶だけを失ってしまう場合もあれば、新しいことを全く覚えられなくなってしまう場合もあります。 また、記憶障害の原因も、加齢、ストレス、脳卒中、アルツハイマー病など、実に様々です。記憶障害は、誰にでも起こりうる身近な問題です。 もし、ご自身や周囲の方が記憶に関するトラブルを抱えていると感じたら、早めに医療機関に相談することが大切です。