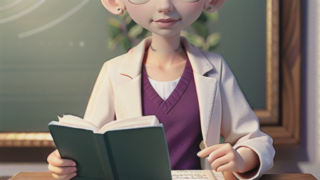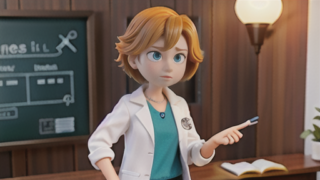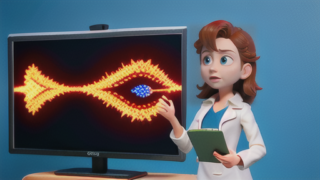脳・神経
脳・神経 錐体外路症状:無意識の運動を司る神経の障害
私たちが思い通りに体を動かせるのは、脳から筋肉へ神経を通して指令が伝わるからです。この指令を伝える経路は大きく二つに分けられ、その一つが「錐体路」と呼ばれる経路です。そして、錐体路以外のすべての経路は「錐体外路」と呼ばれています。
錐体外路は、脳幹と呼ばれる部位にある神経核から脊髄を通って筋肉へとつながっています。この経路は、歩く、物を取るといった動作をスムーズに行うために、姿勢を保ったり、筋肉の緊張を調整したりするなど、私たちが意識しなくてもできる運動をコントロールするという重要な役割を担っています。
例えば、私たちは立っているときに倒れないように、無意識のうちに体のバランスを保っています。また、字を書くときにも、鉛筆を持つ手に適切な力が加えられています。これらはすべて錐体外路のはたらきによるものです。
錐体外路は、運動の開始や停止、力の強弱、動作の滑らかさなどを調節することで、錐体路による運動をより精密なものにするという役割も持っています。錐体路と錐体外路は別々の経路として説明されますが、実際には互いに協調し合いながら、複雑な運動を可能にしています。