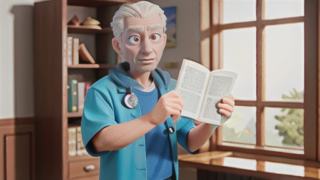皮膚科
皮膚科 知っておきたい性感染症:梅毒
梅毒は、梅毒トレポネーマという螺旋状の形をした微生物によって引き起こされる感染症です。この微生物は、細菌の一種ですが、他の細菌とは異なり、栄養を取り入れるための器官が退化しており、外界では長く生きることができません。そのため、感染経路は、感染している人の粘膜や皮膚に直接触れることに限られます。
具体的には、性行為によって感染することが最も一般的です。感染している人の性器、口、または肛門と直接接触することで、微生物が体内に侵入し、感染が成立します。また、まれではありますが、感染した妊婦から胎児に感染する可能性もあります。
日常生活での接触では感染することはありません。食器やタオルの共用、握手、トイレの便座などを通じて感染することはありませんので、過度に心配する必要はありません。
しかし、梅毒は初期症状が軽いため、感染に気づかずに他の人に感染させてしまう可能性があります。早期発見と適切な治療が重要です。心配な場合は、医療機関を受診し、検査を受けるようにしてください。