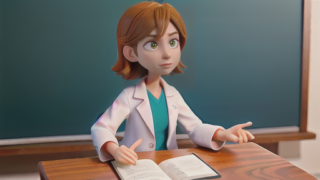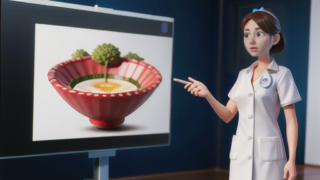産婦人科
産婦人科 出産後の痛み 後陣痛って?
赤ちゃんを産んだ後、多くのお母さんが経験する痛みに「後陣痛」というものがあります。これは、妊娠中に大きく膨らんでいた子宮が、出産を終えて元の大きさに戻ろうと収縮することで起こる痛みです。子宮は、赤ちゃんを十月十日かけてお腹の中で育てられるよう、妊娠中に大きく膨らんでいきます。出産を終えると、その大きな子宮が急速にしぼんでいくため、子宮の筋肉が収縮し、痛みを感じてしまうのです。この痛みは、まるで生理痛がひどい時のような、鈍い痛みであることが多いようです。後陣痛の痛みの強さや続く期間には個人差がありますが、多くの場合、出産後2~3日程度で落ち着いてきます。中には1週間ほど続く方もいらっしゃいます。後陣痛は、決して珍しいものではなく、出産を終えた女性の体が正常に回復しているサインと言えます。しかし、痛みがひどい場合や、不安に感じる場合は、我慢せずに医師や助産師に相談するようにしましょう。