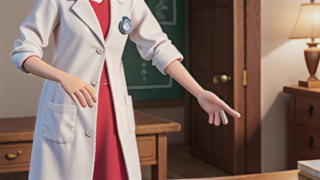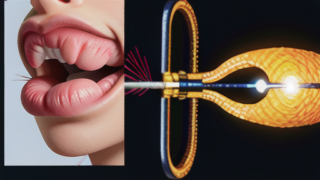薬
薬 皮膚の救世主!ローション剤の効果と種類
- ローション剤とは?ローション剤は、皮膚に直接塗ることで効果を発揮する外用薬の一種です。水のようにさらさらとした液状で、皮膚に塗布しやすい点が特徴です。塗った後は、成分が皮膚から体内に吸収されたり、皮膚の表面に留まって効果を発揮したりします。ローション剤には、様々な種類が存在します。薬効成分が水に完全に溶け込んでいるものもあれば、細かい粒子の状態で水に分散しているものもあります。また、水と油が混ざり合った状態のものもあり、その形態は多岐に渡ります。ローション剤は、その特性から、広範囲の皮膚症状に用いられます。例えば、湿疹や皮膚炎、かぶれ、虫刺されなど、炎症やかゆみを伴う症状に効果を発揮します。また、乾燥肌に対して、皮膚に潤いを与える保湿剤としても使用されます。ローション剤は、一般的に安全性が高いとされていますが、薬効成分の種類や濃度によっては、皮膚への刺激やアレルギー反応が出る可能性もあります。そのため、使用する前に、医師や薬剤師に相談し、自分の肌質や症状に合ったものを選ぶことが大切です。