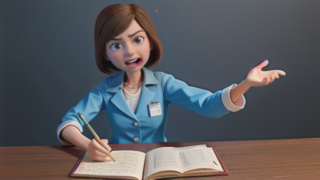循環器
循環器 冠状動脈疾患集中治療室:心臓を守る最前線
心臓疾患専門の集中治療室(CCU)は、心臓に疾患を持つ患者さんの命を守るための重要な役割を担っています。ここでは、冠動脈疾患などの深刻な心臓病を抱えた患者さんに対し、集中的な治療と注意深いケアが提供されます。
CCUは、病院の中でも特に重要な部署の一つです。心臓疾患の専門医である循環器内科医をはじめ、高度なトレーニングを受けた看護師、薬の専門家である薬剤師、医療機器の操作に精通した臨床工学技士など、多くの医療従事者がチームを組んで24時間体制で患者さんの状態を監視し、必要な医療を提供しています。
CCUでは、心電図や血圧、酸素飽和度などの生体情報を常時監視し、患者さんの状態の変化に迅速に対応できる体制が整えられています。また、人工呼吸器や心臓カテーテルなどの高度な医療機器も備えられており、必要があればすぐに使用できる状態になっています。
CCUは、心臓病の緊急事態に対応するだけでなく、手術後や重い心臓発作後の患者さんの回復を助ける役割も担っています。 CCUでの集中的な治療とケアは、患者さんの命を救い、健康を取り戻すために不可欠なのです。