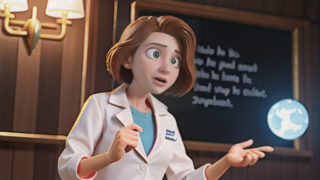循環器
循環器 心房性期外収縮とは?
私たちの心臓は、まるで体の中に組み込まれた時計のように、一定のリズムを刻んで血液を全身に送り届けています。この規則正しいリズムは、心臓の一部である洞結節という場所から発生する電気信号によって作り出されています。しかし、この精巧なシステムも、様々な要因によって乱れてしまうことがあります。このような心臓のリズム異常は、不整脈と呼ばれ、その中には期外収縮も含まれます。
期外収縮は、本来心臓が収縮するタイミングとは異なる時に、心臓が prematurely beatしてしまう現象を指します。多くの人は、期外収縮が起こっても、胸がドキドキする、脈が飛ぶといった軽度の自覚症状を感じる程度で、深刻な問題を引き起こすことは稀です。しかし、期外収縮が頻繁に起こる場合や、他の心臓病を患っている場合には、注意が必要です。期外収縮の原因を探り、適切な治療を行うことが重要になります。