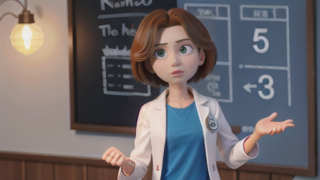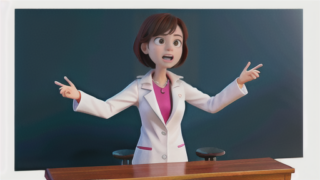その他
その他 原因不明の不調、不定愁訴とは?
- 不定愁訴とは
不定愁訴とは、頭痛、疲労感、消化不良、めまいなど、様々な体の不調を訴えるものの、病院で検査を受けても、その原因となる病気が見つからない状態を指します。
例えば、激しい頭痛に悩まされて病院を受診したとします。医師は念のため、頭部のCT検査や血液検査など、様々な角度から原因を探りますが、検査結果には異常が見られず、頭痛の原因を特定できない場合があります。このような場合に、不定愁訴と診断されることがあります。
不定愁訴は、検査で客観的な根拠が見つからないため、周囲から理解を得られにくいという側面があります。「気のせいなのではないか」「もっとしっかり検査してもらった方がいい」などと言われることもあり、患者は大きな不安やストレスを抱えがちです。
不定愁訴の原因は、まだはっきりとは解明されていませんが、ストレスや不安、生活習慣の乱れ、環境の変化などが関与していると考えられています。そのため、医師は、患者から詳しく話を聞き、生活習慣やストレス状況などを把握した上で、治療方針を決定します。
治療には、薬物療法と並んで、カウンセリングや生活指導など、心と体の両面からのアプローチが重要となります。患者自身が自分の状態を理解し、医師と協力しながら治療を進めていくことが大切です。