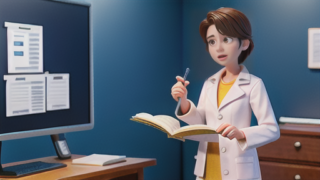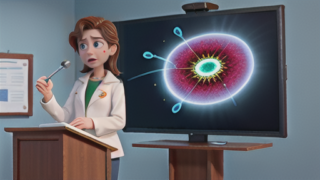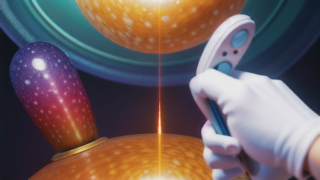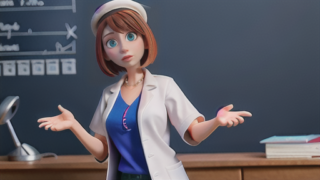生活習慣病
生活習慣病 サイレントキラー!脂質異常症とは?
- 脂質異常症とは脂質異常症とは、血液中に含まれる脂肪の成分である脂質のバランスが乱れた状態を指します。脂質は、体のエネルギー源となったり、細胞膜を構成したりするなど、私たちの体にとって重要な役割を担っています。しかし、これらの脂質が適正なバランスでなくなってしまうと、様々な病気を引き起こすリスクが高まります。脂質には、大きく分けてコレステロールと中性脂肪があります。コレステロールには、「悪玉コレステロール」と呼ばれるLDLコレステロールと、「善玉コレステロール」と呼ばれるHDLコレステロールの2種類が存在します。LDLコレステロールは、血管の内側に溜まりやすく、動脈硬化の原因となることが知られています。一方、HDLコレステロールは、血管に溜まったLDLコレステロールを回収し、肝臓へ運んでくれる役割を担っています。そのため、LDLコレステロール値が高い状態やHDLコレステロール値が低い状態は、動脈硬化のリスクを高める要因となるのです。また、中性脂肪もエネルギー源として重要な役割を担っていますが、血液中の濃度が高くなりすぎると、これもまた動脈硬化のリスクを高める一因となります。脂質異常症は、これらのLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪のいずれか、あるいは複数が基準値から外れている状態を指します。脂質異常症は、自覚症状がほとんどないため、健康診断などで指摘されて初めて気付くというケースが多く見られます。しかし、放置すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる病気のリスクを高める可能性があります。そのため、脂質異常症と診断された場合は、医師の指示に従って、食生活の改善や運動療法など、適切な対策を講じることが重要です。