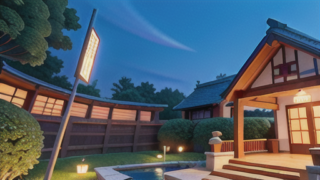泌尿器
泌尿器 排泄障害:原因と対策について
- 排泄障害とは私たちが毎日食事をして生きていく上で、不要になったものや老廃物を体外へ排出することは非常に重要です。 このうち、尿や便として排出する行為を排泄といいますが、様々な原因によってこの排泄がスムーズに行えなくなる状態を、排泄障害といいます。排泄障害には、尿に関するものと便に関するものの二つに大きく分けられます。尿に関するものでは、尿意はあるのにうまく排泄できない、一回の排尿量が少なく何度もトイレに行ってしまう頻尿、反対に排尿回数が少なく一日を通しての尿量が極端に減ってしまう乏尿、排尿後に膀胱内に尿が残っている感覚がある残尿感などが挙げられます。便に関しては、便が硬く排泄に時間がかかってしまう、反対に水分量が多く軟便や下痢が続く、十分に排泄した感覚がないのに、その後も排便できないなどの症状が現れます。これらの症状は、日常生活においてトイレの回数が増えたり、外出を控えるようになるなど、生活の質を著しく低下させてしまう可能性があります。また、排泄の悩みを周囲に相談できずに一人で抱え込んでしまうことで、精神的な苦痛や不安感に繋がってしまうケースも見られます。 排泄障害は、加齢に伴って生じやすくなるだけでなく、生活習慣や食生活、ストレスなども大きく影響します。 一人で悩まず、少しでも気になる症状があれば、医療機関を受診し相談するようにしましょう。