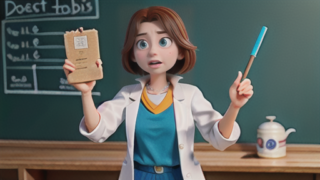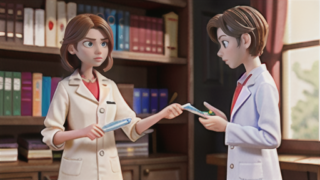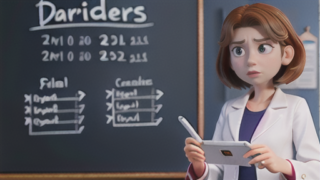脳・神経
脳・神経 ジスキネジア:意図しない動きとその対処
- ジスキネジアとは?ジスキネジアは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう症状を指します。 まるで操り人形のように、自分の意思とは無関係に体が勝手に動いてしまうため、日常生活に様々な支障をきたすことがあります。 この不随意運動は、顔の表情筋、口、舌、手足など、体の様々な部位に現れる可能性があります。 例えば、顔面にジスキネジアが現れると、顔をしかめたり、舌を出したり、口をパクパクさせたりといった症状が現れます。また、手足にジスキネジアが現れると、腕が勝手に動いたり、足がばたばたしたりすることがあります。ジスキネジアの原因は様々ですが、大きく分けて二つあります。一つは、パーキンソン病などの神経疾患に伴って起こるケースです。もう一つは、統合失調症などの治療薬の副作用として現れるケースです。ジスキネジアは、それ自体が病気というわけではありません。 あくまで、他の病気の症状として現れたり、薬の副作用として現れたりする症状の一つなのです。 そのため、ジスキネジアの治療には、まずその原因を突き止めることが重要になります。そして、原因疾患の治療や、副作用を引き起こしている薬の変更などを行うことで、症状の改善が期待できます。