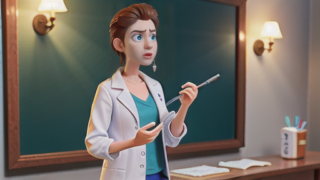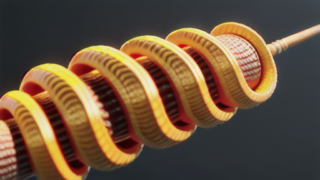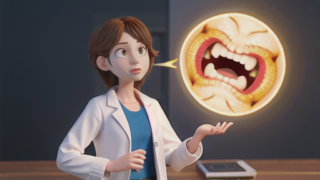消化器
消化器 食中毒を防ぐために
食中毒とは、食べ物に付着した細菌やウイルス、有害な化学物質などを口にすることで、体調が悪くなる病気のことを指します。代表的な症状としては、吐き気や嘔吐、下痢、腹痛などが挙げられます。 食中毒の原因は多岐に渡り、大きく分けて細菌やウイルス、寄生虫といった微生物によるもの、農薬や食品添加物などの化学物質によるもの、フグ毒や毒キノコなどの自然毒によるものの3つに分類されます。
中でも細菌やウイルスによる食中毒は、気温や湿度が上昇する夏場に多く発生する傾向があります。これは、高温多湿な環境が、これらの微生物にとって増殖しやすい条件となるためです。
食中毒を予防するためには、食品の購入から調理、保管に至るまで、あらゆる段階で注意を払う必要があります。例えば、肉や魚などの生鮮食品は新鮮なものを選び、持ち帰る際は保冷剤を入れたクーラーボックスなどを使用し、低温を保つように心がけましょう。また、調理の際にはしっかりと加熱し、食品の中心部まで火を通すことが重要です。さらに、調理器具は清潔なものを使用し、生野菜などは流水でよく洗い流してから食べるようにしましょう。
食中毒は、適切な予防策を講じることで、その多くを防ぐことが可能です。日頃から食中毒のリスクを認識し、安全な食品の取り扱いを心がけましょう。