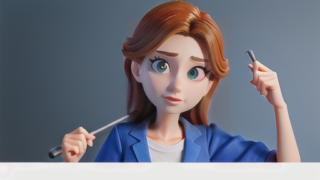その他
その他 病気の物語:現病歴の重要性
- 現病歴とは
現病歴は、医療現場において非常に重要な情報源であり、「今の病気の物語」と表現されることがあります。これは、患者さんが現在抱えている病気や症状について、その発症から現在までの経過を詳細に記録したものです。
具体的には、いつ、どのような状況で、どのような症状が現れ始めたのか、その症状がどのように変化してきたのか、などを時系列に沿って記録します。例えば、発熱の場合、いつから熱が出始めたのか、何度まで上がったのか、他に症状はあったのか、などを記録します。
現病歴は、医師が病気の原因や診断の手がかりを得るために重要なだけでなく、適切な治療方針を決定するためにも欠かせない情報です。そのため、患者さんは医師の診察を受ける際に、現在の症状だけでなく、過去の病歴や症状の変化についてもできるだけ詳しく伝えるように心がけましょう。