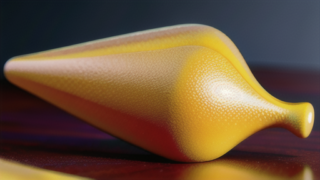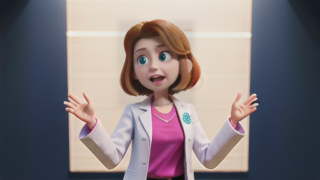検査
検査 混合静脈血酸素飽和度:全身の酸素状態を知る指標
- 混合静脈血酸素飽和度とは私たちの身体は、心臓から送り出された血液によって、全身に酸素を供給しています。心臓から送り出される血液は大動脈を通り、毛細血管を通じて体の隅々まで酸素を運びます。そして、各組織で使われた血液は、最終的に心臓に戻ってきます。この心臓に戻ってきた血液を混合静脈血と呼びます。混合静脈血酸素飽和度(SvO2)とは、この混合静脈血に含まれるヘモグロビンのうち、酸素と結合している割合を示した値です。ヘモグロビンとは、血液の中で酸素と結びつくことで、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。 SvO2は、組織でどのくらい酸素が使われたか、逆にどのくらい酸素が残っているのかを知るための指標となります。 SvO2の値が高い場合は、組織で酸素があまり使われずに残っている状態を示します。逆に、SvO2の値が低い場合は、組織で多くの酸素が使われたことを意味し、組織への酸素供給が不足している可能性も示唆します。 つまり、SvO2は全身の酸素の状態を知るための重要な手がかりとなるのです。