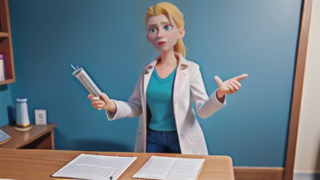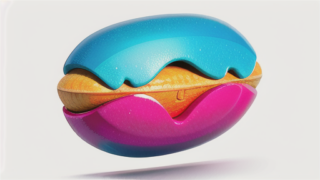検査
検査 医療現場の略語:Dxって?
医療の世界では、正確な情報伝達が欠かせません。しかし、限られた時間の中ですべてを丁寧に説明することは容易ではありません。そこで活躍するのが「Dx」のような略語です。
Dxは「診断」を意味する英語「Diagnosis」を短縮した言葉で、医療現場で頻繁に使用されています。カルテや診療記録など、医療従事者同士が情報を共有する際に、Dxという略語を用いることで、簡潔かつスムーズなコミュニケーションが可能になります。
例えば、患者のカルテに「Dx肺炎」と記載されていれば、その患者は肺炎と診断されたことが一目でわかります。このように、Dxは医療従事者にとって、情報を効率的に理解し、共有するための重要なツールと言えるでしょう。
ただし、医療現場以外では、Dxはあまり一般的ではありません。そのため、患者さんとの会話で使用する際には、誤解を避けるために「診断」という言葉に置き換えるなど、状況に応じて使い分けることが重要です。