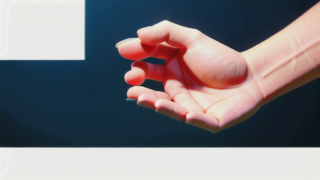検査
検査 放射線とは?医療における役割と種類
- 放射線の定義放射線とは、エネルギーが空間を伝わっていく現象のことを指します。私たちの身の回りには、様々な形でエネルギーが伝わっています。例えば、太陽の光や温かさ、携帯電話に使われる電波なども、エネルギーが空間を伝わってきたものです。これらの現象は全て、広い意味で放射線と捉えることができます。しかし、一般的に「放射線」と呼ばれる場合は、物質を透過したり、原子に影響を与えたりする性質を持つ、より高いエネルギーのものを指すことが多いです。レントゲン撮影に使われるエックス線や、原子力発電に関わるガンマ線などが、この高いエネルギーを持つ放射線の代表例です。放射線は、目に見えたり、臭いを感じたりすることはできません。しかし、物質を透過する性質を利用して、レントゲン写真のように体の内部を調べたり、工業製品の検査に利用されたりしています。また、原子に影響を与える性質は、医療分野ではがん治療などにも応用されています。このように、放射線は私たちの生活に深く関わっており、様々な分野で利用されています。しかし、高エネルギーの放射線は、人体に影響を与える可能性もあるため、適切な取り扱いと理解が重要です。