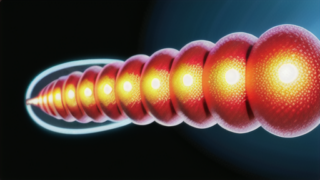呼吸器
呼吸器 身体の守護者:肋骨の役割と構造
私たちの胸部には、心臓や肺といった重要な臓器を保護するために、かごのような骨組みが存在します。これが肋骨です。肋骨は左右に12本ずつ、合計24本あり、背中側では背骨、胸側では胸骨という骨と繋がっています。
肋骨は、その形状から「あばら骨」と呼ばれることもあり、緩やかにカーブを描いた弓のような形をしています。この弓形が、鳥かごのように胸部全体を覆うことで、外部からの衝撃から臓器を守っているのです。
また肋骨は、呼吸をする際にも重要な役割を担っています。息を吸うと肋骨は上に持ち上がり、胸郭と呼ばれる胸部の空間が広がります。逆に息を吐くと肋骨は下がり、胸郭は縮小します。この肋骨の動きによって肺に空気が出入りし、私たちは呼吸をすることができるのです。
このように肋骨は、私たちの身体にとって非常に重要な役割を果たしています。身体を支える支柱としての役割と、呼吸を助ける役割、そして心臓や肺を守る役割を同時に担っているため、肋骨はまさに「縁の下の力持ち」といえるでしょう。