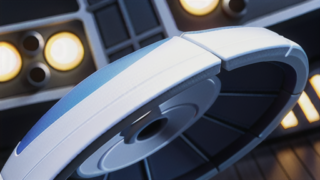血液
血液 身近に潜む危険! ヘマトーマとは?
- ヘマトーマってどんなもの?ヘマトーマとは、体の組織内に血液が漏れ出て、溜まった状態のことを指します。 例えば、転んで頭を強く打ったり、スポーツ中に激しく転倒したりすると、その衝撃で血管が損傷し、血液が周りの組織に漏れ出てしまうことがあります。この血液が皮膚の下に溜まり、青紫色に変色して腫れ上がった状態が、まさにヘマトーマなのです。ヘマトーマは、その大きさやできる場所によって、症状が大きく異なります。 皮膚のすぐ下にできた小さなヘマトーマであれば、痛みも少なく、時間の経過とともに自然に吸収されていくことが多いです。 しかし、頭蓋内や内臓など、体の奥深い場所で大きなヘマトーマができた場合は、命に関わる危険性もあります。一般的に、ヘマトーマは青紫色に変色することが多いですが、時間の経過とともに、赤紫色、緑色、黄色と変化していきます。これは、ヘモグロビンという血液中の赤い色素が分解される過程で、色が変化していくためです。 また、ヘマトーマ周囲の組織は、血液によって刺激され、炎症を起こしているため、痛みや熱感を伴うことがあります。ヘマトーマは、程度の差はあれ、誰にでも起こりうる身近なものです。 しかし、症状が重い場合や、なかなか治らない場合は、自己判断せずに、医療機関を受診するようにしましょう。