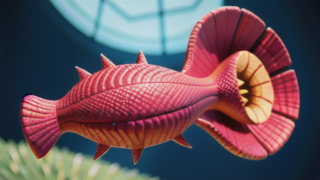薬
薬 生理食塩水:私たちの体液と似た働きをするもの
- 生理食塩水とは私たちの体の中にある血液や体液には、ほぼ一定の濃度の塩分が含まれており、体の機能を正常に保つ上で非常に重要です。生理食塩水は、この体液の塩分濃度とほぼ同じ濃度に調整された、0.9%の塩化ナトリウム水溶液のことを指します。生理食塩水が医療現場で頻繁に使用される理由は、体液との浸透圧が近く、体への負担が少ないためです。そのため、点滴によって体内の水分や塩分を補給したり、薬剤を溶かして投与する際の溶解液として用いられます。また、注射の際に針を刺す部位の消毒や、傷口を洗い流す際にも使用されます。さらに、医療現場以外でも、コンタクトレンズの洗浄液など、私たちの身近なものにも生理食塩水は利用されています。このように、生理食塩水は、その安全性と汎用性の高さから、医療現場のみならず、様々な場面で活躍しています。