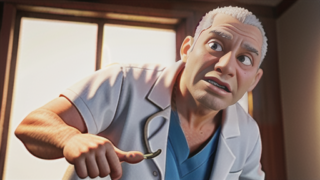救急
救急 災害医療の現場で活躍するトリアージタグ
災害や事故現場では、同時に多数の負傷者が発生することがあります。このような状況では、限られた医療スタッフと資源を最大限に活用し、一人でも多くの命を救うことが何よりも重要となります。しかし、病院のように設備や人員が十分に整っているわけではないため、医療現場では迅速かつ的確な判断が求められます。 そこで、傷病者の治療優先順位を決定するために用いられるのが「トリアージ」と呼ばれるシステムです。
トリアージでは、負傷者の呼吸状態、循環状態、意識レベルなどを基に、重症度を4段階に分類します。 そして、それぞれの重症度に応じて、黒、赤、黄、緑の4色のタグを付けます。黒は救命の可能性が低い、赤は生命の危険があり直ちに処置が必要、黄色は重症であるが緊急性は低い、緑は軽症で後回しにしてもよい、というように、色で治療の緊急度を示すのです。
例えば、呼吸が停止している、大量出血が続いているといった場合は、一刻を争う事態であるため、「最優先治療群」として赤色のタグが付けられます。一方、骨折や切り傷など、命に関わらない場合は、緑色のタグを付け、比較的症状が落ち着いている他の傷病者の治療を優先します。
このようにトリアージは、限られた医療資源の中で、一人でも多くの命を救うために、非常に重要な役割を担っているのです。