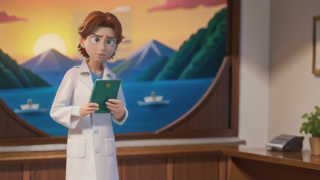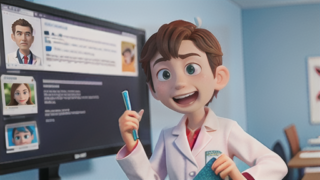脳・神経
脳・神経 てんかん:脳の電気信号の乱れが引き起こす発作
- てんかんとはてんかんは、脳の神経細胞が一時的に過剰に興奮することによって起こる病気です。この過剰な興奮は、脳波の異常として記録され、様々な症状を引き起こします。この症状を「発作」と呼びます。発作には、意識を失って全身が硬直したり、手足が痙攣する「大発作」や、一瞬意識がぼーっとするだけの「欠神発作」など、様々な種類があります。発作の症状は、脳のどの部分が過剰に興奮するかによって異なります。てんかんは決して珍しい病気ではなく、世界中で約5000万人が罹患していると推定されています。日本では人口の約1%、およそ100万人がてんかんを抱えていると考えられており、誰にでも起こりうる病気と言えます。てんかんの原因は様々で、脳腫瘍や頭部外傷、脳血管障害などが原因で発症する場合もあれば、原因が特定できない場合もあります。 てんかんは、適切な治療を行うことで発作をコントロールし、普通の生活を送ることが可能な病気です。てんかんの治療には、薬物療法や外科療法など、様々な方法があります。