血管の危険!塞栓症とは?

病院での用語を教えて
先生、『塞栓子』って何か教えてください。

体の健康研究家
そうだね。『塞栓子』は簡単に言うと、血管を詰まらせてしまう物質のことだよ。例えば、血管の中で血液が固まってしまったものとかが考えられるね。

病院での用語を教えて
血管が詰まるってことは、体にとって良くないことですよね?

体の健康研究家
その通り。塞栓子によって血管が詰まってしまうと、血液がその先に流れなくなってしまい、体のあちこちに様々な問題を引き起こす可能性があるんだ。これが『塞栓症』だよ。
塞栓子とは。
「医学や健康で使う『塞栓子』という言葉について説明します。『塞栓子』とは、血管が詰まる原因となるものです。『塞栓物』とも呼ばれます。血管を詰まらせるものには、血のかたまり、腫瘍、脂肪、空気など、いろいろなものが考えられます。塞栓子によって血の流れが止まってしまうことを『塞栓症』といいます。
血管を塞ぐもの

私たちの体の中には、まるで網の目のように張り巡らされた血管があり、血液が体内をくまなく巡っています。この血液は、生命維持に欠かせない酸素や栄養を体の隅々まで運び届ける役割を担っています。しかし、何らかの原因でこの血管が詰まってしまうことがあります。その結果、血液が行き渡らなくなった組織は酸素や栄養が不足し、深刻な状態に陥ってしまうのです。
では、一体何が血管を詰まらせてしまうのでしょうか?血管を塞いでしまう物質を塞栓子と呼びますが、その正体は様々です。
最も一般的な塞栓子は、血液の塊である血栓です。血管が傷ついたり、血流が悪くなったりすると、血液が固まって血栓ができやすくなります。この血栓が血管から剥がれて流れ出し、細い血管に詰まってしまうことがあります。
また、悪性腫瘍の一部が剥がれ落ち、血流に乗って別の場所に運ばれて血管を詰まらせることもあります。さらに、脂肪や空気なども塞栓子となることがあります。例えば、骨折をした際に骨髄中の脂肪が血管に入り込んだり、医療ミスで血管内に空気が入ってしまったりすることがあります。
このように、血管を塞ぐ原因は多岐に渡り、命に関わる危険性も孕んでいます。日頃から血管の健康を意識し、血流を良好に保つことが重要です。
| 塞栓子の種類 | 説明 |
|---|---|
| 血栓 | 血管が損傷したり、血流が悪くなると血液が固まってできる。これが剥がれて流れ出し、細い血管に詰まることがある。 |
| 悪性腫瘍の一部 | 悪性腫瘍の一部が剥がれ落ち、血流に乗って別の場所に運ばれて血管を詰まらせる。 |
| 脂肪、空気 | 骨折時に骨髄中の脂肪が血管に入ったり、医療ミスで血管内に空気が入ったりする。 |
塞栓症とその種類

– 塞栓症とその種類血管は、体中に酸素や栄養を運ぶ重要な役割を担っています。しかし、様々な原因で血管が詰まってしまうことがあります。これを塞栓症と言います。 塞栓症は、血管の中で血液の流れを阻害する物質(塞栓子)が血管に詰まることで発生します。塞栓症を引き起こす原因には、大きく分けて3つの種類があります。* -血栓性- 血管の中で血液が固まってしまった血の塊(血栓)が原因となるものです。* -非血栓性- 空気や脂肪、腫瘍細胞など、血液以外の物質が血管に詰まることで発生するものです。* -その他- 異物や薬剤などが血管に詰まることで発生するものです。塞栓症は、どの血管が詰まるかによって、引き起こされる症状や病気は様々です。 例えば、脳の血管が詰まれば脳梗塞、心臓の血管が詰まれば心筋梗塞、肺の血管が詰まれば肺塞栓症を引き起こします。 また、足の血管が詰まれば、歩行時に足が痛む閉塞性動脈硬化症を引き起こすこともあります。塞栓症は命に関わる危険な病気も引き起こす可能性があります。そのため、早期発見、早期治療が非常に重要です。 普段から、生活習慣の改善などを行い、塞栓症を予防することが大切です。
| 塞栓症の種類 | 原因 | 起こりうる病気の例 |
|---|---|---|
| 血栓性塞栓症 | 血管の中で血液が固まったもの(血栓) | 脳梗塞、心筋梗塞、肺塞栓症、閉塞性動脈硬化症 |
| 非血栓性塞栓症 | 空気、脂肪、腫瘍細胞など、血液以外の物質 | – |
| その他 | 異物や薬剤など | – |
塞栓症の症状

– 塞栓症の症状塞栓症は、血管が血の塊によって詰まることで様々な症状が現れます。症状は、詰まった血管の種類や場所によって大きく異なります。脳の血管が詰まった場合、脳梗塞を引き起こします。脳梗塞の症状は突然現れることが多く、激しい頭痛やめまい、手足の麻痺、言葉の障害、ろれつが回らない、意識障害などがみられます。顔の半分が麻痺したり、片方の目が見えにくくなったりすることもあります。脳梗塞は命に関わる病気であるため、このような症状が出た場合はすぐに救急車を呼ぶ必要があります。肺の血管が詰まった場合は、肺塞栓症を引き起こします。肺塞栓症では、息切れや胸の痛み、咳、血痰などがみられます。息苦しさは、動くとひどくなる傾向があります。 また、足の血管に血栓ができた場合に、その血栓が肺に飛んで肺塞栓症を引き起こすことが多く、その場合は足のむくみや痛みを伴うこともあります。肺塞栓症も命に関わる病気であるため、これらの症状が出た場合はすぐに医療機関を受診する必要があります。心臓の血管が詰まった場合は、心筋梗塞を引き起こします。心筋梗塞は、心臓の筋肉に血液が送られなくなる病気です。心筋梗塞の症状は、胸の痛みや圧迫感、冷や汗、吐き気、息切れ、意識消失などです。突然死のリスクも伴う危険な状態であるため、これらの症状が出た場合はすぐに救急車を呼ぶ必要があります。塞栓症は命に関わる病気であるため、早期発見・早期治療が重要です。少しでも異変を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
| 塞栓症の種類 | 症状 |
|---|---|
| 脳梗塞 | 突然の激しい頭痛、めまい、手足の麻痺、言葉の障害、ろれつが回らない、意識障害、顔の麻痺、片方の目が見えにくいなど |
| 肺塞栓症 | 息切れ、胸の痛み、咳、血痰、足のむくみや痛み |
| 心筋梗塞 | 胸の痛みや圧迫感、冷や汗、吐き気、息切れ、意識消失 |
塞栓症の原因
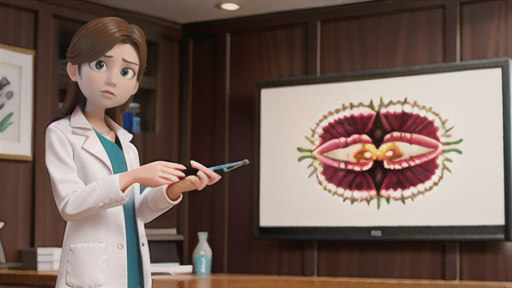
塞栓症は、血管が何らかの物質によって詰まってしまうことで起こる病気です。この詰まりの原因となる物質を塞栓といい、様々なものが考えられますが、最も多いのは血の塊である血栓です。
では、なぜ血栓ができてしまうのでしょうか? 健康な状態であれば、血液は体内を滞りなく流れています。しかし、血流が悪くなると、血液が固まりやすくなってしまいます。例えば、長時間同じ姿勢を続けることは、血流を悪化させる大きな要因となります。デスクワークや長距離移動など、現代人にとっては身近なものがリスクになり得るのです。
また、血管の内壁が傷ついている場合も、血栓ができやすくなります。血管を傷つける原因としては、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が挙げられます。これらの病気は、血管に負担をかけ、もろくしてしまうのです。
さらに、喫煙も血管を傷つけ、血栓のリスクを高める要因の一つです。タバコに含まれる有害物質は、血管の内壁を傷つけ、炎症を引き起こします。
塞栓症は、命に関わることもある恐ろしい病気です。日頃から、血流を良くし、血管を健康に保つように心がけましょう。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などを意識することが大切です。
| 塞栓症の原因 | 詳細 |
|---|---|
| 血栓 | 血液が固まって血管が詰まる。長時間同じ姿勢、血管内壁の損傷などが原因となる。 |
| 血流悪化 | 長時間同じ姿勢、運動不足などが原因となる。 |
| 血管内壁の損傷 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが原因となる。 |
塞栓症の予防
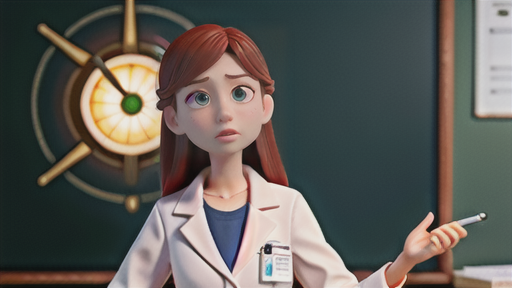
– 塞栓症の予防
塞栓症は、血管の中で血液が固まってしまうことで起こる病気で、生命に関わる危険性もはらんでいます。しかし、日々の生活習慣を見直し、予防に努めることで、そのリスクを大きく減らすことができます。
まず、喫煙は血液をドロドロにし、血管を傷つけるため、禁煙することが非常に重要です。また、適度な運動は血液の循環を良くし、血管の健康を保つために効果的です。激しい運動である必要はなく、毎日無理なく続けられる程度の運動を心掛けるようにしましょう。
食生活においても、塩分や脂肪を控え、野菜や果物を中心としたバランスの良い食事を摂ることが大切です。そして、水分をこまめに摂取することで、血液の粘度を下げ、流れをスムーズにすることができます。
長時間同じ姿勢で作業をする場合は、定期的に立ち上がって体を動かしたり、軽いストレッチを行うようにしましょう。特にデスクワークや長時間の乗り物移動の際は、注意が必要です。飛行機での旅行時には、エコノミークラス症候群の予防のためにも、こまめに席を立って歩く、足を動かすなどの対策を心がけましょう。医師の指示があれば、弾性ストッキングの着用も有効な予防策となります。
塞栓症は、日々の心がけによって予防できる病気です。健康的な生活習慣を送り、積極的に予防に取り組みましょう。
| 予防策 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 生活習慣の改善 | – 禁煙 – 適度な運動(毎日継続できる程度) – 塩分・脂肪控えめ、野菜・果物中心のバランスの良い食事 – こまめな水分摂取 |
| 長時間同じ姿勢を防ぐ | – 定期的に立ち上がり、体を動かす – 軽いストレッチを行う – デスクワークや長距離移動時に特に注意 |
| その他 | – 医師の指示があれば弾性ストッキングの着用 |
早期発見と治療

– 早期発見と治療
血管の中にできた血の塊(血栓)が流れ、血管を詰まらせてしまう病気を塞栓症と言います。この病気は、脳、心臓、肺など、体の重要な器官で起こることがあり、命に関わる危険性もはらんでいます。しかし、早期に発見し、適切な治療を行うことができれば、救命できる可能性が高まります。
塞栓症は、初期の段階では自覚症状が現れない場合もありますが、突然、激しい頭痛やめまい、手足の痺れ、言葉が出にくい、息苦しい、胸が痛いなどの症状が現れることがあります。これらの症状は、他の病気でも見られることがありますが、塞栓症の可能性も考え、すぐに医療機関を受診することが重要です。
医療機関では、症状や診察、検査結果に基づいて診断を行います。塞栓症と診断された場合は、血栓を溶かす薬や血液をサラサラにする薬を使用する薬物療法、カテーテルという細い管を使って血栓を取り除くカテーテル治療など、症状や重症度に応じて適切な治療が行われます。
塞栓症は、早期発見と早期治療が非常に重要です。「もしかしたら・・・」と思ったら、ためらわずに医療機関に相談しましょう。
| 塞栓症とは | 症状 | 診断 | 治療 |
|---|---|---|---|
| 血管内でできた血栓が流れ、血管を詰まらせる病気。脳、心臓、肺などの重要な器官で起こり、命に関わる危険性も。 |
|
症状、診察、検査結果に基づいて診断 |
|

